赤ちゃんの成長スピードは人それぞれ、と分かっていても「いつ頃から寝返りが始まるのか目安が知りたい」というパパママは多いですよね。
また、目安の時期とずれていることで不安に思われる方もいるでしょう。
この記事では、寝返りをする時期の目安や前兆、練習方法や注意点について解説していきます。
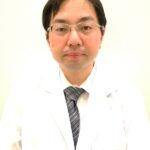
武井 智昭
2002年 慶應義塾大学医学部卒業。2002年から2004年まで慶応義塾大学病院研修医。2004-2011 平塚共済病院 内科・小児科医長。2012年より神奈川県内のクリニックを経て、2017年なごみクリニック院長、2020年高座渋谷つばさクリニック院長(内科・小児科・アレルギー科)
武井先生の監修した記事一覧
https://kodomonosiro.jp/specialist/specialist-2054/
寝返りはいつごろ始まる?
「寝返り」とは、赤ちゃんが自力で仰向けからうつぶせになれることを言います。
生後3〜4か月で首がすわり、次の発達段階として「寝返り」があります。
寝返りが始まる一般的な時期や早い場合、遅い場合についても見ていきましょう。
平均的には5〜6か月
厚生労働省の調査では、5〜6か月では、86.6%の赤ちゃんが寝返りができるようになるという結果が出ています。
下記表を見ても、寝返りができるようになるのは、平均的には5〜6か月と言えるでしょう。
| 年齢 | 寝返りが出来るようになった子どもの割合 |
|---|---|
| 2ヶ月~3ヶ月未満 | 1.1% |
| 3ヶ月~4ヶ月 | 14.4% |
| 4ヶ月~5ヶ月 | 52.7% |
| 5ヶ月~6ヶ月 | 86.6% |
| 6ヶ月~7ヶ月 | 95.8% |
| 7ヶ月~8ヶ月 | 99.2% |
| 8ヶ月~9ヶ月 | 98.0% |
早い子だと3か月頃から
平均的には、寝返りの時期は5〜6か月ですが、早い子は3か月ごろから寝返りをはじめます。
上記表を見ても、4か月時点で寝返りができる子が少なくとも15%程度いることがわかります。
首すわりと同時期に寝返りをするケースもあるようです。
早産児など6か月以降のケースも
早産で産まれた場合など、生後6か月以降に寝返りを始める子もいます。
早産で産まれた赤ちゃんの発達や成長を見る際には、修正月齢を使いましょう。
修正月齢とは、産まれた日ではなく出産予定日を基準に計算する月齢です。
例えば、出産予定日の2か月前に産まれた赤ちゃんであれば、
- 生後1か月の時点では、修正月齢はマイナス1か月
- 生後3か月の時点では、修正月齢は1か月
となります。
正期産でも、産まれる期間は37週〜41週と1か月も幅があります。
寝返りをする時期はあくまで目安としてとらえ、焦りすぎず見守りましょう。
寝返りの兆候・サイン

赤ちゃんは、頭から足に向かって身体機能が発達していきます。
目や頭を動かせるようになり、次に肩や腕を動かし手をばたつかせるようになります。
だんだんと背中や腰もしっかりしてきて、体ごとひねる・反らすなどの大きな動作もできるようになります。
一般的には、以下の4つが寝返りを始めるサインといえます。
- おもちゃや人を目で追うようになる
- 仰向けの状態で手足をよく動かす
- 体をひねる動作をする
- 自力で横向きになれる
おもちゃや人を目で追うようになる
「パパやママの声がする方を向きたい」「興味のあるおもちゃを見たい」といった欲求から興味関心がある対象を目で追うようになり、自分で動くモチベーションにもなります。
おもちゃをゆっくりと移動させるなどまずは赤ちゃんが「目で追う」機会を増やしていくのがおすすめです。
赤ちゃんが向いている方向の反対側からたくさん話しかけてあげるのも有効です。
言葉の発達を促すことにもなり、一石二鳥です。
仰向けの状態で手足をよく動かす
最初は寝転んだままの赤ちゃんも、次第に機嫌の悪さや喜びを手足をバタつかせて表現するようになります。
仰向けの状態でも、手足の力でズリズリと移動するようになったら背中や腰の筋肉が発達してきている証拠です。
体をひねる動作をする
左右どちら向きでも、仰向けからうつ伏せに体勢を変えられることを「寝返りができた」と言います。
寝返りをする過程では、体をひねる動作が必要です。
体をひねろうとしたり、反る動作が見られたら寝返りに成功する日も近いです。
自力で横向きになれる
体をひねって自力で横向きになれたら、後はうつ伏せになるだけなので寝返りできるようになったも同然です。
体をひねった反動でそのままうつ伏せの体勢になることもあるので、この過程を経ずに寝返りができるようになる子もいます。
寝返りの練習方法
寝返りの練習を始める時期や具体的な練習方法をご紹介していきます。
寝返りの練習はいつ頃から?
発達には個人差があり、寝返りの練習を始めるのに決まった時期はありません。
また、寝返りをする前に腹ばいに移行する子もいます。
遊びの中で自然と体を動かしながら発達を促すのが良いでしょう。
うまく横向き、うつ伏せに体勢を変えられなくて泣き出してしまう赤ちゃんもいます。
手を添えてサポートしたり、腕が変な位置にないかどうかも確認してあげましょう。
1.おもちゃや声がけをして目で追わせる

お気に入りのおもちゃや色鮮やかなおもちゃを見せて、ゆっくりと動かしながら目で追わせるようにします。
赤ちゃんが向いている方向とは反対の方向から声をかけ、声のする方に顔を向かせるのも効果的です。
自分で動きたい、という思いが寝返りをするモチベーションになります。
そのためにも、赤ちゃんの興味・関心を引かせるような遊びや声かけを取り入れると良いでしょう。
2.目の動きに合わせて腰や背中を支え横向きに
赤ちゃんの真横におもちゃを置いて、目だけでなく体全体で興味・関心のある方向を向けるように、腰や背中を支えながら横向きになるのをサポートします。
体をひねる、あるいは反る動きを見せている時は練習のチャンスです。
この時、押すのではなく手を添えるくらいにします。
赤ちゃんに体の動かし方を知ってもらうためです。
左右でバランスよくやっていきましょう。
3.体をひねり横向きからうつぶせになる練習

まずは、赤ちゃんの顔を左右どちらかに向けます。
次に、横向きになったときに上にくる足をもう一方の足の上に置きます。
右方向に向くのであれば、左足を立てるように右足のうえに置くイメージです。
そこから足を交差させながら反動を使って回転させます。
途中でそっとお尻に手を添えたら、そのまま横向きからうつ伏せまで体勢を変えることができます。
横向きになった時に下側の手が抜けていないようだったら、そっと抜いてあげましょう。
4.寝返り返りの練習
「寝返り返り」とは、寝返りをしてうつぶせになった状態からさらに寝返りをして仰向けに戻ることをいいます。
自力でうつ伏せから仰向けに戻る動作ができるようになると、長時間うつ伏せでいることが減るため、窒息やSIDSの危険性が少し緩和されるでしょう。
寝返り返りができるようになるのは、寝返りをした1か月~1か月半ほどたった後と言われています。
うつ伏せの姿勢から頭を上げたり、腹ばいで過ごす時間を少しずつ増やしていったりしながら寝返り返りに必要な筋力をつけていきましょう。
寝返りを始めたら注意すべきこと
寝返りをするようになったら注意すべき点を見ていきます。
思わぬ事故を防ぐためにも、寝返りをする前兆が見られたら環境を整えておきましょう。
柔らかいものに注意
赤ちゃんが自力でうつ伏せに体勢を変えられるようになったら窒息に注意しましょう。
- 大人用の柔らかい布団やベッドでは寝かせない
- クッションなど柔らかいものを置かない
この2点を徹底しましょう。
タオルも絡まったり巻きついたりする可能性があるので、なるべく置かないようにしましょう。
寒さ対策をする場合には、タオルをかけるのではなく、スリーパーを着せるのが望ましいです。
小さいものを置かない
寝返りを始めたころの赤ちゃんは好奇心も旺盛になり、興味が惹かれるものを口に運んで確かめるようになります。
小さいものは誤飲を防ぐためにもそばに置かないようにしましょう。
特に上の子がいる場合には注意が必要です。
上の子の年齢にもよりますが、赤ちゃんの周りに小さいものを置かないように言って聞かせたり、遊び終わったら一緒にお片づけをしたりするのも事故防止になります。
また、ベビーベッドやベビーサークルで赤ちゃんがいるスペースを区切っておくと安心です。
ベビーベッドは柵を上げておく

仰向けの状態でも、手足を使って移動するうちに予想外の位置にいることがあります。
寝返りをするようになると、さらにベビーベッドの端から転落する可能性が高まります。
短時間であっても、目を離す際はベビーベッドの柵をしっかりと上げておきましょう。
同様に、ソファや大人用のベッドにひとりで寝かせるのも危険です。
段差がなく落下物の危険がない床にマットをしいて寝かせておくのが安心です。
睡眠中の寝返り対策
SIDS(乳幼児突然死症候群)は、健康だった赤ちゃんが睡眠中に突然亡くなってしまう病気です。
SIDSの原因は呼吸停止や不整脈など原因は不明でありますが、厚生労働省のガイドラインによれば、あおむけ寝よりも、うつ伏せ寝の赤ちゃんの方がSIDSの発症率が高くなるといいます。
■1歳になるまでは、寝かせる時はあおむけに寝かせましょう
SIDS は、うつぶせ、あおむけのどちらでも発症しますが、寝かせる時にうつぶせに寝かせたときの方が SIDS の発症率が高いということが研究者の調査から分かっています。医学上の理由でうつぶせ寝を勧められている場合以外は、赤ちゃんの顔が見えるあおむけに寝かせましょう。この取組は、睡眠中の窒息事故を防ぐ上でも有効です。
とはいえ、仰向けで寝かせていても、気づいたらうつ伏せになっていることもあります。
赤ちゃんが寝ている間ずっと見張っているわけにはいきませんが、気づいたらその都度仰向けに直してあげましょう。
赤ちゃんの呼吸に異常がないか見守るグッズもあります。
異常があった際にはアラームが鳴って気づかせてくれるので、活用してみると良いでしょう。
※参考商品※ 乳児用体動センサ ベビーアラーム E-201

https://www.babysmile.ne.jp/babyalarm
寝返りの時期に関するよくあるQ&A
首座り前に寝返りすることはある?
首が座る前に寝返りをする子もいれば、首すわりと寝返りがほぼ同時という子もいます。
一般的には、首すわり、寝返り、おすわり、ずりばい、ハイハイと進んでいきますが、順番が前後する赤ちゃんもいます。
順番が前後したからといって過度に心配する必要はありません。
寝返りをしない…小児科受診を検討すべきはいつ頃から?
成長には個人差があり、寝返りをする時期も赤ちゃんによってばらつきがあります。
ただ、厚生労働省の調査では、99%の赤ちゃんが生後7~8か月までに寝返りをすると報告されています。
生後8か月を過ぎても寝返りの兆候が見られない場合には、小児科を受診しましょう。
診察を受ける際は、寝返りの兆候があるかの参考にするため、普段の様子やできることできないことを医師に伝えるのが望ましいです。
寝返りが早いのは要注意?発達が早いってこと?
寝返りをする時期が平均に比べて早いと「何か異常があるのでは?」と心配になるかもしれませんが、単に発達が早い、というケースがほとんどです。
寝返りが早い点以外にも気になることが複数ある場合は、小児科受診の際や健診時に聞いてみるのもいいでしょう。
また、発達障害との関係性を疑い心配される方もいますが、相関性はないとされています。
寝返りがいつ始まってもいいように準備を

寝返りは一般的には生後5~6か月頃から始まりますが、発達には個人差があります。
遅いからといって過剰に心配する必要はありませんが、赤ちゃんの機嫌がよいときに遊びの一環で寝返りの練習をするのもいいでしょう。
赤ちゃんが寝返りをするようになると安全対策にもより一層気を配る必要があります。
- ベッド周りや部屋の片づけをこまめに行う
- 赤ちゃんを高い位置に置く場合は目を離さない
この2点を徹底すれば、窒息や誤飲、転落といった事故を防げます。
早い場合には生後3か月頃から寝返りを始める子もいるため、いつ寝返りを始めてもいいように早めに環境を整えておきましょう。
#寝返り #赤ちゃん寝返り #SIDS












